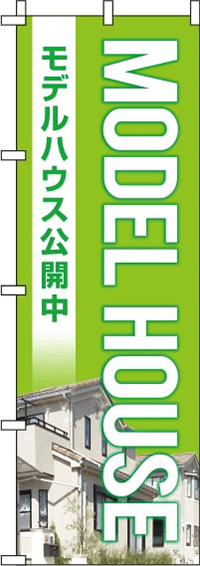写真入りのぼり旗でアピールしよう!写真を使うメリットと作成時のポイント

目次
写真入りののぼり旗を使うメリット
写真入りののぼり旗と文字だけののぼり旗では、見た目の華やかさだけでなくお客さんが受け取るイメージに大きな差が出ます。写真入りののぼり旗にはたくさんのメリットがありますよ。
写真があることでイメージがしやすい
文字だけではどうしてもイメージのわかないメニューは、写真があると一目瞭然です。

最近は「チーズタッカルビ」「スンドゥブ」といったような民族料理や多国籍料理が売りのお店がありますので、そののぼり旗を作る時には写真を入れることをおすすめいたします。
また、地方のお土産や名産品ののぼり旗も写真があった方がイメージしやすいです。
オリジナルの写真を使えば他店と差別化できる
お店でこだわっているメニューがあるのなら、その写真を撮影してのぼり旗に入れるのもおすすめです。
例えば「海鮮丼」を売りにしたいなら、どんな海鮮を使っているのかもわかりやすいですし、文字だけを入れた他店ののぼり旗と比べると写真があるのぼり旗のお店に入りたいという人の方が多いでしょう。
また、食べ物のイラストだとどうしても実際出てきた料理と異なる場合もあるため、 写真入りののぼり旗の方がお店に対する信頼度が上がります。
キャッチコピーや文字を入れなくても伝えたいことがわかりやすい
のぼり旗に伝えたいことをすべて盛り込みたい気持ちはわかりますが、キャッチコピーをいくつも入れてしまうとのぼり旗が文字で埋まってしまい、何を伝えたいかがぼやけてしまいます。
また、視認性にも乏しくなってしまいます。
キャッチコピーは最小限に留め、一目で伝わる写真を入れ視覚に訴えた方が伝わりやすいでしょう。
写真入りののぼり旗を作成するポイント
写真入りののぼり旗を作る際、配色やレイアウトをきちんと確認しましょう。
闇雲に作っても、却ってわかりづらくなってしまっては本末転倒です。
視認性にすぐれ、集客効果が高い写真入りののぼり旗の作成ポイントは以下の通りです。
配色は2~3色以内にする
写真そのものがカラフルなため、のぼり旗に派手な色を使おうとすると写真が目立たなくなってしまいます。
のぼり旗そのものはシンプルに2~3色でまとめるようにしましょう。
背景色と文字色のバランスも大切です。
黄色の背景色なら赤、赤の背景色なら白、といった組み合わせが合います。
写真は適切な解像度にする
入稿の際に提出する写真データの質にも気をつけましょう。
どのぐらいの密度でその写真が構成されているかを「dpi」という単位で表したものが「解像度」と呼びます。
dpiの値が高いほど密度が濃く、印刷した時に鮮明に映ります。
一般的にのぼり旗に使う写真は原寸サイズで150dpi以上の解像度があれば鮮明に印刷されます。
300dpiを超えると肉眼ではほとんど見分けがつかないといわれており、入稿の際に送るファイルも重くなってしまいます。


データを入稿する際は150~200dpiの解像度のものを使用することを推奨します。
また、写真を撮る際は白い布の上に置くなどして不要なものを写さないようにすると、画像処理がしやすくなります。
写真や文字のレイアウトを工夫する
デザインをする際に、のぼり旗のどこに写真と文字を配列するかも大事です。
人は、縦のものを見るときは上から下へ目線を移すことによって認識します。
一番下に置かれたものを強く認識する習性があるため、ポイントとなる写真は下の方に置くようにしましょう。
長い文字数は案外読まれないため、多くても7文字までに留めます。
生地にこだわる

軽く発色が良いため人気ですが、こだわりの写真を印刷するのなら、生地を変えてみるとよりきれいなのぼり旗を作ることができます。

発色も良く、写真もきれいに印刷されるためタペストリーなどに使われている素材です。
裏抜けがないため、裏側から見た時写真やデザインを確認することはできませんのでテトロンツイルを使う場合はそこだけ注意しましょう。
写真入りののぼり旗は、視認性に富むだけではなく店主のこだわりをふんだんに詰め込むことができます。
手作り感のあるオリジナリティーに溢れた写真入りののぼり旗で、ぜひお店のアピールをしましょう。